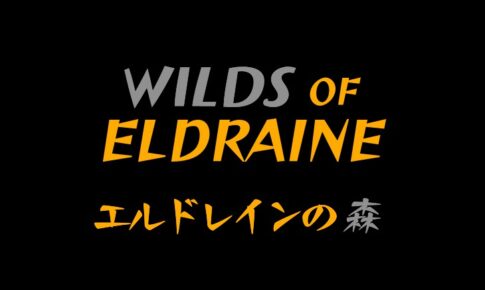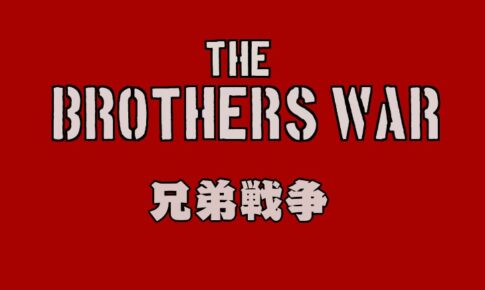今回から、1発目の記事は”ルールまとめ”に統一する事にしました。初見の感想は別記事で書く予定。
カードギャラリーは以下
https://magic.wizards.com/ja/products/the-lost-caverns-of-ixalan/card-image-gallery
メカニズムの確認
リリースノートから気になるところを抜粋。
■『イクサラン:失われし洞窟』リリースノート
新メカニズム:作製
『イクサラン:失われし洞窟』のアーティファクトの一部は、作製と呼ばれる起動型の能力を持っている。
- 作製能力は、コストとしてマナに加えて「素材」も必要とする起動型能力である。
- 作製能力は「[素材]で作製[マナ]」と書かれており、以下がテンプレ構文。
[マナ], このパーマネントを追放する, あなたがコントロールしているパーマネントやあなたの墓地にあるカードの中から[素材]を追放する:このカードをオーナーのコントロール下で変身させた状態で戻す。起動はソーサリーとしてのみ行う。
- 一部の作製を持つカードの第2面は、「作製に使った」カード(=作製能力起動時に併せて追放したカード)を参照する。作製を持つカードが戦場に残っているかぎり、作製に使った情報は保持される。作製を持つカードのコントローラーが変わったり、その特性の一部が(たとえば、コピー効果によって)変わったりしても作製に使われた情報は失われない。
- 素材に複数のオブジェクトを要求される場合、コントロールしているパーマネントと墓地にあるカードの両方から追放するカードを選んでももよい。
- あなたがコントロールしているトークンを素材として追放してもよい。
- トークンは追放領域に残らないため、第2面の「作製に使った」素材を参照する能力は機能しない。
- 変身する両面カードでないカードが作製を持つカードのコピーになっていて、それの作製能力を起動した場合、それは追放領域に留まり戦場に戻らない。
※変身する両面カードについては割愛
新キーワード処理:発見
『イクサラン:失われし洞窟』のカードには「発見(数値)」のキーワード処理が存在する。
- 「発見Nを行う」と、「マナ総量がN以下であり土地でないカード1枚が公開されるまで、あなたのライブラリーの一番上から1枚ずつ追放していく。そのカードが『発見された』カードである。あなたは「発見されたカード」をマナ・コストを支払うことなく唱えてもよい。そうしないなら、そのカードをあなたの手札に加える。残りの追放されたカードをあなたのライブラリーの一番下に望む順番で置く。
- 呪文のマナ総量は、それのマナ・コストのみによって決まる。代替コスト、追加コスト、コスト増加、コスト減少は無視する。
- あなたが発見を行ったとき、あなたはカードを追放しなければならない。
- 発見の解決中は表向きにカードを追放し、対戦相手も見ることができる。
- 「マナ・コストを支払うことなく」呪文を唱えるなら、代替コストの支払いを選択することはできない。
- 追加コストを支払うことはできる。呪文に強制の追加コストがあるなら、それを唱えるためにはそれを支払わなければならない。
- 発見されたカードのマナ・コストに{X}が含まれるなら、マナ・コストを支払うことなくそれを唱えるときのX=0。
- 適正な対象がないなどの理由で唱えられない場合、その発見したカードをあなたの手札に加える。
- あなたに発見を行わせる呪文や能力の中には、対象を必要とするものがある。選ばれたすべての対象がその呪文や能力の解決時に不適正な対象であった場合、この能力は解決されず、あなたは発見を行わない。
- 分割カードのマナ総量は、両サイドのマナ・コストの和。
- 発見によって分割カードを唱える場合は、片方だけ唱える事ができる。
- 当事者カードや分割カードやモードを持つ両面カードを発見した場合、その効果の発見の値によってはそのカードのいずれかの特性でそれを唱えることができるかもしれない。
- 例:発見4を行い、《通電の巨人》(マナ総量が4である『エルドレインの森』の当事者カード)を公開したなら、《通電の巨人》を唱えることができるが、《嵐読み》(マナ総量が7であるそれの出来事)は唱えることができない。⇒発見7であれば両方を選択可能
新メカニズム:落魄
新能力語:落魄N/底なしの落魄
落魄は、いずこかから墓地に置かれたパーマネント・カードの枚数を参照する新しいルール用語である。
- このターンにいずこかからパーマネント・カードを墓地に置いたプレイヤーを「このターンに落魄したプレイヤー」と呼ぶ。
- このターンにプレイヤーが落魄した枚数を参照するカードが存在する。
- このターンにいずこかからそのプレイヤーの墓地に置かれたパーマネント・カードの枚数を参照する。
- 落魄を参照する際に、墓地に残っているかどうかはチェックしない。
- パーマネント・カードにトークンは含まれない為、トークンが墓地に置かれても、プレイヤーが落魄したことには含まれない。
- 「あなたの終了ステップの開始時に、このターンにあなたが落魄していた場合、」から始まる能力を持つカードは、あなたが落魄した時点でコントロール下になくても条件を満たす。
- 例えば、あなたの第1メイン・フェイズ中にパーマネント・カードがあなたの墓地に置かれ、あなたがあなたの第2メイン・フェイズ中に《鍾乳石の追跡者》を唱えた場合、あなたの終了ステップの開始時に、これの能力が誘発する。
- 「あなたの終了ステップの開始時に、このターンにあなたが落魄していた場合、」から始まる能力は、あなたの終了ステップ中に一度だけ誘発する。あなたがこのターンに落魄した回数は関係ない。
- ただし、あなたの終了ステップの開始時にあなたが落魄していなかった場合、能力は一切誘発しない。
- 終了ステップ中に、能力の誘発に間に合うようにパーマネント・カードを墓地に置くことはできない。
- 「落魄N」という能力語を持つカードは、あなたの墓地にN枚以上のパーマネント・カードがあるかどうかを見る能力を持っている。
- 「底なしの落魄」という能力語を持つカードは、あなたの墓地にパーマネント・カードが何枚あるかを見る能力を持っている。
- 一部の落魄の誘発型能力には「場合のルール」が含まれる(能力の中に「あなたの墓地に[4か8]枚以上のパーマネント・カードがある場合、」と書かれている)。これらの能力は、誘発する瞬間にあなたの墓地を見て、その時に誘発するかどうかを見る。
- その時点で必要な枚数のパーマネント・カードがあなたの墓地になければ、その能力は一切誘発しない。
- 誘発した場合、その解決時点で再度チェックする。その時点で必要な枚数のパーマネント・カードがあなたの墓地になければ、その能力は解決されず、その効果は発生しない。
新メカニズム:地図・トークン
- 地図・トークンは定義済みトークンの一種であり、アーティファクト・サブタイプ「地図」と「{1}, {T}, このアーティファクトを生け贄に捧げる:あなたがコントロールしているクリーチャー1体を対象とする。それは探検を行う。起動はソーサリーとしてのみ行う。」の能力を持つ無色のアーティファクトである。
新メカニズム:最終カウンター
- 最終カウンターは、クリーチャーだけでなく、すべてのパーマネントに置く事ができる。最終カウンターが置かれているパーマネントが戦場から墓地に行くなら、代わりにそれを追放する。
- 最終カウンターは、パーマネントが戦場から墓地でない領域に行くことを阻止しない。たとえば、最終カウンターが置かれているパーマネントが戦場からオーナーの手札に戻るなら、それは通常通り行われる。
- 最終カウンターはキーワード・カウンターではないため、それが置かれたパーマネントに何らかの能力を与えたりしない。そのパーマネントが能力を失ったあとで墓地に置かれる場合でも、代わりに追放される。
- 1つのパーマネントの上に複数の最終カウンターがあっても意味はない。