ブログを再開したタイミングの影響で、イコリア環境はいきなり「まとめ」から始まってしまいますが、今後も気長に続けられるようであれば、
- カードセットが出たタイミングで「雑感」を書いて
- 少し間をあけて今回のような「まとめ」を書いて
- 忘れたころに「その後」を書く
といった環境の煮詰まりによって変遷していく考え方を記録できればいいなぁ、とぼーっと考えています。なので、今回はひとまず環境のファーストインプレッションを思い出しながら書いていこうと思います。
環境初期の振り返り
「エルドレインの王権」環境がライブラリアウトで溢れて嫌気がさした反動もあって、前回の「テーロス還魂記」環境はそれなりの回数を楽しくこなしていました。その為、久しぶりに1つ前の環境に身体が慣れすぎている状態だったと今思えばわかります。(具体的には「イロアスの恩寵」を巡る4ターン目までの攻防が一つの目安になる、序盤の立ち上がりを意識する環境)
ミンス先生が記事を執筆してくれた影響も手伝って、環境初期は赤白のサイクリングをピックする事が多く、緑を嫌って意図的に点数を下げていました。赤白サイクリングは”勝ち方”を理解していないプレイヤーでは受けにくい構造になっている為、かなり勝率が高かった印象があります。(実際、かなり早い段階でミシックに到達しました。)
低いマナ域のサイクリングにシナジーを持つ強力なアンコモンから先行して、リソースが切れたら「天頂の閃光」を探しにいって逃げ切る。
1か月終えての感想
変容生物の評価手法の転換
今環境の大きな特徴として、コモンにインスタントの完全除去が4マナで用意されている事が挙げられます。このため、デッキ全体を変容生物によるテンポ獲得に寄せすぎると、一枚の完全除去でプランが瓦解したり、カードアドバンテージを失ってリソース切れを起こしやすくなる事が想像に難くありませんでした。
当初は、変容生物を変容コストのみで評価してしまっていた為、先述のデメリットを看過できない事に結び付けて、工夫無く変容を重ねる戦術をピック時点で放棄してしまっていました。この戦術に欠陥がある事は現在も異論はありませんが、そのせいで変容生物自体の評価を下げる事にはならない訳です。変容生物を本来のマナコストで評価して、変容能力を戦術的なオプションだと再整理した事で、緑系デッキの勝率は大幅に改善しました。
わかりやすい例として「洞窟で囁くもの」を挙げると、変容で出すと相手が手札を捨てるので、後で除去を打たれても1対1交換が成立してアドバンテージを失っていないから出しやすいと理解していました。カードの枚数としては確かに正解なのですが、例えば相手が捨てた手札が”余っている土地”だった場合は、この交換は適正だと言い難く(=交換の質が相手の選択に依存する)、生物が集約する結果として相手の除去やブロッカーも集約できる=相手を楽にさせる行動となり得ます。過去のキーワード能力「授与」と比較すると、程よいデザインになっている事がわかります。場に出たら相手が一枚捨てる効果を持つ、1~3のサイズアップ&威迫を付与するオーラだと言い換えると、あまり使いたくないカードに見えるようになりました。
授与:クリーチャーとして唱えるかオーラとして唱えるかを選ぶことができるキーワード能力。オーラとして戦場にあるときもエンチャント先がいなくなると自動でクリーチャーになるので、オーラ特有のカード・アドバンテージの損失もない。その分、授与コストは全体的に重めに設定されている。
http://mtgwiki.com/wiki/%E6%8E%88%E4%B8%8E(M:TG WIKIより抜粋)
重視すべきはテンポより盤面の構築
先の変容生物の評価基準整理を一歩進めると、この環境はテンポの獲得より盤面の優位を重視した方が良いとい考えられます。除去が強くてマナフラッドへの対策が極端に少ない環境なので、除去の的を一つに集約する変容の使いどころは慎重に選びたいです。
もう少し具体的な例を出すと、ターンを伸ばして恒常的にアドバンテージが獲得できるシステムの構築をする事をゴールに設定した方が負けにくいと言えそうです。「頑丈なダンゴムシ」と「野生肉の密猟者」のコモンコンボなどが良い例かと。
カード評価の側面で言えば、序盤から終盤まで役割を持てるカード(=ゲームを通して手札で腐るタイミングが少ない)の評価は上げて、特定の場面に限定されるが特化した強さが見込まれるカードの評価は下げたいところです。
カラーコンビネーションの格差
3色がテーマとなった今回のセットにおいて、多色のカードは友好色をレアに、対抗色をアンコモンにそれぞれ割り振られています。上下で完全に2色が一致するシチュエーションはかなり稀な事から、対抗色のマルチカードを複数枚拾う期待値は高いと言えそうです。このため、レアリティが高いカードを多くふくむという軸においては、対抗色の方が優位であると考えています。
また、多色レアはそのカラーコンビネーションに紐づいたテーマに強く依存している為、後半のピックで拾ってからタッチしにくいというデメリットもあります。
除去の評価基準を変更
試行を重ねる過程で「除去よりも生物を優先する」など、基準を弄りながらピックを行いましたが、結局は完全除去を最優位に置いて、生物の方を妥協する形が良いという結論に落ち着いています。
その分、条件付きの除去については少し評価も変化していて、環境初期と比べて評価を下げたのは「死の重み」と「刃による払拭」でした。どちらも2枚目から大きく点を下げています。ちなみに「火の予言」は、土地の引きすぎへの耐性の関係でむしろ評価があがっているくらい。
死の重み
赤白サイクリングを中心にメタゲームを検討すると、序盤のアンコモン生物をテンポよく潰せる点でかなり優秀だと評価できたのですが、3マナ圏の生物から早くも対象を外れてしまう点が辛い。2マナ以下の生物の重要度は増しているので、1枚ならば打ちどころに困る事は無い印象。
刃による払拭
育った変容生物を捌く用途においてはかなり優秀でしたが、縦に積まずに横に並べる戦術が優位になった事で、当てる事自体が難しくなった上に、コンバットトリックに合わせるには、4マナを構える余裕がないので、2枚引くと憤死する。
Q&T(=Think)
コメントその他で投げ込まれた質問について考えるコーナー。答え(Answer)ではない。
恰好の餌食
死の重みの方がテンポ面で優れており、格好の餌食の評価は死の重みより下か?という質問。
先の死の重みの評価にあるように、除去として対象に入るのは2マナ以下なので役割はほぼ同じで、「死の重み」より1マナ重い代わりにインスタントであり、サイクリングできる。
赤白サイクリングの低マナ生物によるハメパターンを回避する手段でありながら、後半は自力で他のカードに入れ替えられるので、2枚までデッキに入ると思います。「死の重み」と一緒に入っていたら、「格好の餌食」を優先します。
万能のブラッシュワグ
万能のブラッシュワグを複数枚入れるのは痩せすぎではないか?という質問。
序盤は変容によるジャンプアップの条件を満たしながら、マナが伸びた終盤に引いても2回起動で7/7トランプルとして単体で完結して殴れる可能性を秘めている事から、複数枚採用する価値があると考えます。
とりあえず、こんなところで。


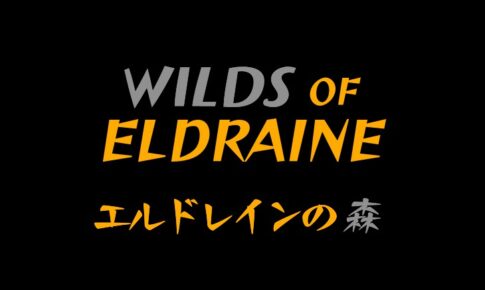



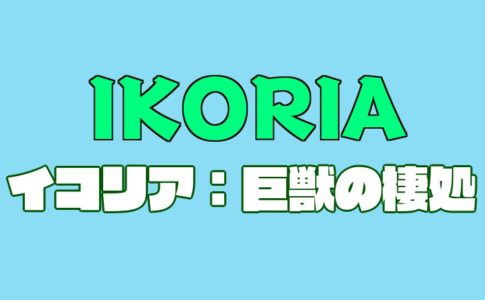

コメントを残す